 味覚とエッセイ
味覚とエッセイ 「ねるねるねるね」考察 ― 幼き職人たちへの第一歩
私がこの駄菓子「ねるねるねるね」と再会したのは、確か姪がまだ幼かった頃のことでした。久しぶりに口にしたその味は、なんとも不思議。酸味の強いラムネの風味が、どこか“飲みすぎた午後の胃酸”のように感じられ、正直なところ、最初は魅力を見出せずにい...
 味覚とエッセイ
味覚とエッセイ 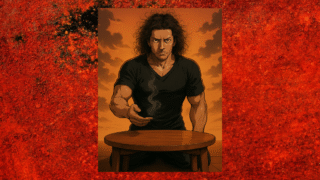 味覚とエッセイ
味覚とエッセイ 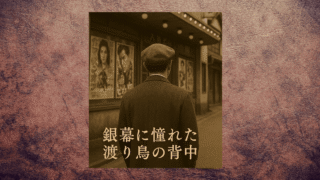 味覚とエッセイ
味覚とエッセイ  味覚とエッセイ
味覚とエッセイ 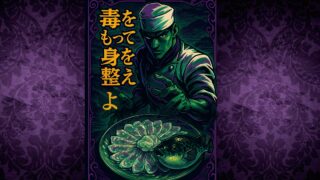 味覚とエッセイ
味覚とエッセイ  味覚とエッセイ
味覚とエッセイ  味覚とエッセイ
味覚とエッセイ  味覚とエッセイ
味覚とエッセイ  味覚とエッセイ
味覚とエッセイ  味覚とエッセイ
味覚とエッセイ